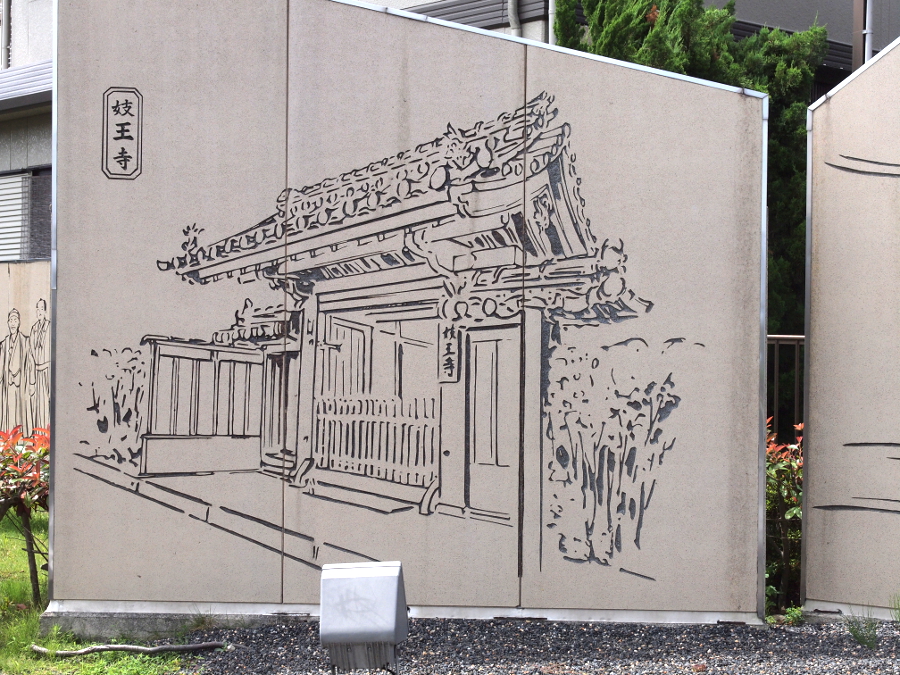城山が
 栗東市六地蔵
栗東市六地蔵日向山登山口の駐車場入り口に階段状の墓地がある。たかだか数mの高さだが、そこへ上ると視界が一気に広がる。田んぼの中にある灌木でふさがれていた視線が、それを越えて奥にある旧東海街道沿いの集落につながるためである。と、ここまでは何度も経験している。今回、この風景を新しく感じたのは、三上山の右裾にちょこんと見える傾いた台形を見たからだった。城山、この山が背後の日光山山頂から見えることは当然のこととして知っていた。しかし、山麓のここから見えるとは夢にも思っていなかった。
いつもは北の野洲市旧中主町や近江八幡市あたりから見て、三上山の左に見えるのが当然の風景と思い込んでいるのだが、反対の南側から見れば右に見えることもある。いつかも湖南市三雲の大沙川沿いから見えて驚いたことがあった。そして三上山のすぐ右側、ぐるっと後ろを回って最初に顔を出すところがここだったのだ。立場の違いで見え方が変わる。人間だれでも自分の立場が当たり前と思いこむ。心したい。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


街道の手品
 湖南市石部西2丁目
湖南市石部西2丁目標題写真(写真A)は、宮川に並行する旧東海道から見た三上山である。手前の風景が変わったので、別の山のように感じるが、手前に菩提寺山の麓が斜めに横切り、その奥に三上山が見える。宮川の岸から見たのと同じ部分が見えている。次に、それから100m余り進んだところから見たところ(写真B)。写真ではわかりにくいが、歩いていると三上山がぐんぐん小さくなっていくのが分かる。実際は三上山の大きさは変わらず、菩提寺山の麓が大きくなっていくのだが。
もう1枚、これは標題写真より30mほど手前、この道を歩いていて、道が三上山に向かいだす初めての地点。緩いカーブを曲がって目の前に三上山が現れるところである(写真C)。三上山が大きく見ることに関しては感動的である。石部から草津へ向かう昔の旅人は残らず目を見張ったのではないか。このときも最初ここで撮ろうとしたのだが、電柱が気になり写真Aを先に撮った。そのあとやっぱり気になって、宮川での写真を撮った後、もう一度ここへ舞い戻ってきた。空の青さの違いはその時間のずれである。
山を大きく見ようとして、近づけば近づくほど小さくなっていくという不思議な場所であるが、写真では表現しきれない。これは実際に歩いてもらう以外どうしようもない。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


山静か
 湖南市石部西2丁目
湖南市石部西2丁目宮川。石部雨山運動公園あたりから流れ出て、石部頭首工に流れ込む小さな河川である。その川が石部西あたりで旧東海道と並行する。ただし、民家が間に入り込むため、街道を歩ていても川の存在に気づかない。私自身も旧東海道は何回も通りながら、昨年秋、宮川そのものをトレースするまでその存在を知らなかったところである。
そのとき野山は紅葉の真最中、今回、夏のこの時期どんな風景に変わっているかと訪ねて行ったというわけ。まあしかし考えてみれば当たり前のこと、褐色が緑に変わっただけ。しかし、7月末のこの時期、真上から照り下ろす夏の太陽が山野に静けさをもたらしていた。新緑のころの”山笑う”に対して、この時期は”山滴る(したたる)”とか”山茂る”などというらしいが、私は”山静か”を感じる。いつの間にかの習慣で、暑いこの時期でもカメラを持って出るのは昼過ぎ。太陽が高い時間帯での感覚であるが。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


お遊び
 湖南市岩根
湖南市岩根湖南市岩根、イオンタウンの近く。ヒマワリ畑があるとシャチョウがいういう。私は気がつかなかったが。よく聞いてみるとと三上山の横にでかい建物があって絵にはならない場所だ。でもそれを無視するとあとの祟りが怖い。何とかしましょうということで、暑いさなかに出かけていった。なるほど咲いている。背の低いいま流行りのやつだ。
建物があることは初めから分かっている。それをどう処理するかだ。あーでもない、こーでもない、といろいろやってみたが、邪魔なものは邪魔、口で言うほど簡単な話ではない。同じ邪魔ならもっとでかい邪魔者で目をそらすか。しょうもないことをいろいろやってみた。最後はどうせ無理なら魚眼風に歪ますか。無理を承知のお遊びである。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


発掘調査中
 野洲市三上
野洲市三上野洲市三上のバイパス予定地。発掘調査が行われている。三上山に向いて農地に「田」の字を書いた時、第4画の水平な線とバイパス予定地が交わるところ。2m近く掘り込まれたところに直径1mあまりの円形の穴が見える。それに流れ込むように見える黒い線は水路だろうか。井戸だとするとそこへ水が流れ込むのはおかしな話だし、円形の穴が自噴していた水源でそれから水が流れだしていたとすると理屈には合う。いつごろのものか分からないがこんなにきれいに円形の穴が掘れるとしたら、そこそこの技術力を持った集団だったというとになるのか・・・。
などと下らないことを考えていたのだが、これが7月21日。それがきょう(7月26日)現場を通ったら、井戸?も川?もきれいに埋め立てられて元の木阿弥。何とまあ世の中のテンポの速いこと。それとも何の値打ちもない遺跡だったのか。穴があったあたりをもう1枚。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


ひとときの風景
 野洲市行畑2丁目
野洲市行畑2丁目家が一軒取り壊された。風景が変わる。道路は三上山を真横に見て走っている。手前に見える縁石は車道と歩道を分けるものである。いままで見にくかった三上山が、まあ何とか見えるようになった。右の奥の電柱は隠せたのだが、不覚。適当の撮ってきたことがありありと見える。撮りなおしに行けばいいのだけど、それほどのものでもないだろう。
右に細い進入路が見える。それをポイントにしたらどうだろう。寄ってみた。これでぎりぎり。家が建っていたころの写真はなかったかと探してみたが、残っていなかった、というよりは撮っていなかったのだろう。これで家が建っていたらやっぱり無理だったろう。この土地がこのまま空き地で残るはずはない。ひとときの風景である。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


ワイドが使えたころ
 野洲市行畑2丁目
野洲市行畑2丁目野洲中央道「行畑」交差点から「大畑」の方へ70mほど進んだところである。実はこの2つの交差点間の距離は500m余りだが、この間三上山が見えるのはこの場所だけである。10年ほど前まではかなりの場所から見えたが、その後住宅が建ち視界は閉ざされた。
1981年1月4日、日の出の少し前。有明の月と金星が上下に並んでいた。見事な風景だった。月はともかく金星は寸刻を争う。当時住まいしていた万葉台住宅の我が家から、一番近いところ。それがこの場所だった。場所のアリバイは左手に見える明かりだけ。確かアパートの灯りだったとの淡い記憶だけである。
標題写真の真正面に見える2階建ての建物。この廊下の照明が有明月の写真では左端に小さく見える。標題写真の撮影位置より、数m右に寄ったところが、1981年の撮影位置である。今そこに立っても三上山は見えない。今昔2枚の距離間の違いはレンズの長さによる。昔がワイド、いま望遠。残念ながら今ここでワイドは使えない。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば


背比べ地蔵
 野洲市小南
野洲市小南野洲市行畑の「背比べ地蔵」。昨日のあずま屋横を通過するアンダーパスが地上へ戻って旧中山道と交差するところにある。地蔵堂は昨日のあずま屋とよく似ているが、こちらは大小2体の地蔵さんが鎮座し、7月末に地蔵祭りがおこなわれる。以前は日が固定されていたが、最近は曜日で決められているようだ。今年は次の日曜日、7月30日がその日に当たる。午後5時から旧中山道と写真に写っている地蔵堂前の通りが歩行者天国になる。
ポスターを見ると”野洲市無形民俗文化財”とある。地蔵さんという実態があるのに何で”無形”なのか。中山道沿いの民家で、農機具を使ってその年の話題になったことをテーマにして”作り物”が展示される。それがこの祭りの目玉なのだが、最近は数が減って”なあかなかむつかしおすわ”、役員さんお声である。
写真ステージ 「近江富士」
■近江非名所全集
■滋賀を歩けば